
|
には、ヒノエウマのために異常に出生数が低かった昭和41年(’66)の1.58をも下回る1.57となり「1.57ショック」という新語さえ生まれました。
平成5年(’93)には1.46にまで低下し、平成6年(’94)には出生数の増加とともに合計特殊出産率も1.50に回復したものの、平成7年(’95)には1.43で人口動態統計史上(明治32年以降)最低となり、依然として出生数・率の低下傾向が続いています。
このように出生率の低下は、中長期的にみてこれがどの程度で推移するか予断を許さない状況にあります。
厚生省人口問題研究所では国税調査の結果をもとに日本の将来推計人口を発表していますが、平成3年(’91)から平成37年(2025)までの34年間をその推計期間とし、高位、中位、低位の将来人口推移を設けており、さらに平成102年(2090)までの参考推計値も付け加えられています。
この推計によると、高位推計では平成3年(’91)年から直ちに上昇に転じ、平成37年(2025)には2.09の水準に到達されるものとしていますが、1.80までに回復するという前提に立つ中位推計では、高齢化のピークは平成56年(2044)の28.4%となっており、平成32年(2020)には4人に1人が高齢者という超高齢化社会の到来といわれています。さらに1.45の水準にとどまるという前提に立つ低位推計によれば、高齢化のピークは平成65年(2050)の33.3%にまで高まり、国民の3人に1人は高齢者という状態になるものと予想されています。(図3、表5、表6)
このように、高齢化とは人口構造が高齢化し、人口に占める高齢者の割合が増加していくことですが、平均寿命が延びて高齢者の数が増加したり、出生率が低下して相対的に若い人口が減少することによっても高齢化は影響を受けます。
図2 出生数及び合計特殊出生率の年次推移
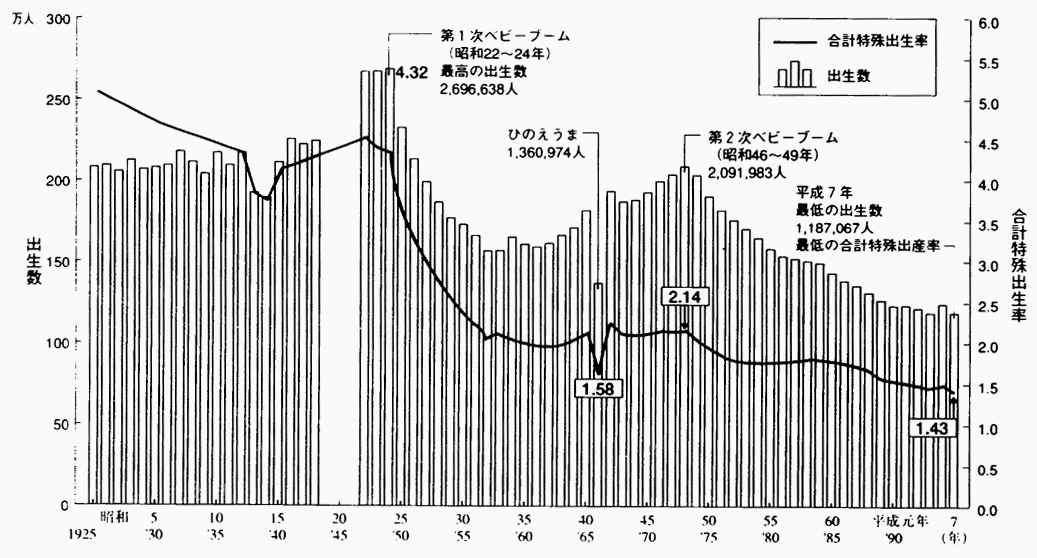
前ページ 目次へ 次ページ
|

|